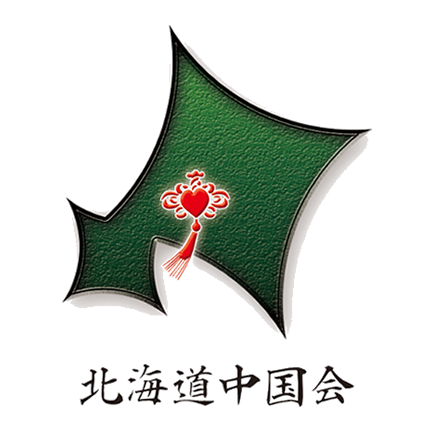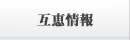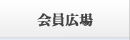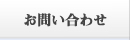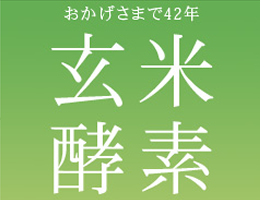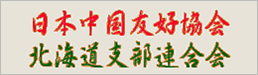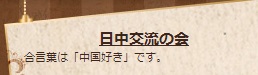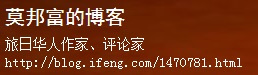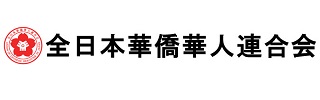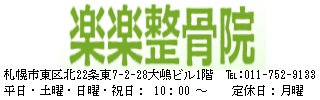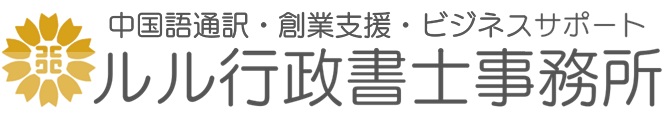高齢化が進む中国・西安で「高学歴の若者」が激増している奇跡
莫 邦富:作家・ジャーナリスト
高齢化が進む中国・西安で「高学歴の若者」が激増している奇跡高齢化が進む中国において、人口流出が激しい東北部よりも環境が厳しい西北部に位置する西安で、ある奇跡が起きている(写真はイメージです) Photo:PIXTA
西安副市長が来日時に語った
高学歴の若者が急増する背景
しばらく前、古代シルクロードの起点で、中国歴代13王朝の都として栄えた西安市から、王勇副市長一行が日本を訪れた。私は銀行出身の王副市長一行を、日本の証券会社をはじめとする金融機関や企業に案内した。
日本企業の関係者との交流の中で、企業誘致の任務を背負っている中国側の自己紹介には、耳にタコができてしまうほど常套句的な内容が多い。たとえばいつも、交通の便利さ、労働力の豊富さ、賃金の安さ、市場の大きさなどが強調される。
しかし、今回の王副市長の発言には面白い内容があり、それが私の関心を惹いた。彼が西安市の人口規模に触れたとき、2018年の1年間で、西安市には新住民といわれる市民が80万人も増えたという。また市民の平均年齢は37.39歳で、前年度よりは1歳も下がった。こうした話を、彼は誇らしげに紹介した。
つまり、新市民の中に若い人が多いから、市全体の人口の平均年齢を押し下げてくれたのだ。急速に高齢化社会となりつつある中国では、住民の平均年齢の若さがセールスポイントとなる。
もう1つ、王副市長は新市民の中身も強調した。新市民の構造を見ると、若いだけではなく、学歴も高い。その40%は大卒である。同市の大学卒業者の62.9%が西安に残りたいと言っているという調査データも、誇らしげに見せた。
その発言を聞きながら、私は中国に存在する「東北現象」と呼ばれる現象を思い起こした。ここでいう「東北」とは、旧満州だった黒竜江省、吉林省、遼寧省のことをいう。その東北現象は、つまり地域経済のマイナス成長、地元人口の他の地域への流失を表現する新語だ。
東北よりもっと環境が厳しい西北にある西安は、なぜ東北現象が起こらずに済んだのかと疑問に思う人もいるだろう。西安には大学が84校ある。大学在学生は130万人以上もいる。その大卒の若者の大半が西安に残ることを希望しているという現実が、西安の「若さ」を維持してくれた。だから、「大学が多いことが西安を窮地から救った」という説明を聞いたこともある。
高齢化社会を迎えた中国では、住民の平均年齢が若いことが都市の競争力になっているのだ。王副市長の発言を聞きながら、そのことを再度、認識させられた。
さらに深く考えると、すぐに次の現象に気づいた。中国の各地方、各都市間の競争のポイントは、これまでのGDPや企業誘致実績から、人口の増減という新しい分野へとシフトしている。しかも、その現象がすでに広く見られている。
人的移動のハードルを
壊した戸籍政策の大変動
その背後には、中国の戸籍政策の大きな変動という流れがある。今年3月に発表された『2019年新型都市化建設重点任務』という文書からも、その政策変化の一端を覗くことができる。わかりやすくいえば、中国は全面的に大型都市の戸籍登録条件を緩和し、正式に全国都市化を開始する、という号令が出されたのだ。
中華人民共和国が成立してから、中国はずっと厳しい戸籍制度を実施してきた。農村に居住している人間は農村戸籍しかもらえず、都市部への移住が厳しく制限されてきた。都市戸籍を持つ都市部の住民にとっても、規模の大きい都市への移住が非常に困難だった。
1978年から改革・開放時代が始まって、40年以上が経った。その40年間はある意味で、これまでの戸籍制度との闘いの40年間ともいえる。経済の活性化は人的流動の活発化を促進し、さらにその人的流動の活発化は、頑なに一元的な管理の下にに置かれている戸籍制度の障壁を打ち破る作業へとつながっていく。つまり改革・開放時代の40年間は、戸籍制度の解体作業の40年間ともいえる。
それでも、これまでの市街地の人口500万以上の都市では、戸籍は厳格に制限されていた。しかし今、その風向きは突然変わってきた。常住人口が100万~300万人の大都市では、全面的に戸籍制限がなくなり、人的移動のハードルはゼロとなった。常住人口が300万~500万人の大都市では、全面的に戸籍制限が緩和される。北京、上海、広東、深センなどの超大型都市では、「積分落戸制度」(ポイント政策)を整え、大幅に新市民の受け入れ枠、つまり戸籍枠を増加した。これらの大都市で真面目に仕事をしている人間なら、ほぼ間違いなくその都市の戸籍を確保できるようになったのだ。
北京、上海、深センなどに加えて、広州、天津、成都、武漢、南京、鄭州、杭州などの都市部の戸籍制限も、すべて大幅に緩和された。
日本社会を苦しめている少子高齢化の現象は、中国でも見え始めた。それはさらに「住民争奪戦」を熾烈なものにした。その意味では、住民争奪戦は数年前にすでに始まっていたのだ。国としての政策変更は、その現実を追認しただけのようなものだ。
瀋陽、ハルピン、青島、西安、合肥、昆明、太原、長春、大連、長沙、済南、アモイ、南寧、ウルムチ、蘇州、寧波、石家庄、南昌、貴陽、汕頭、蘭州、無錫、福州、洛陽、仏山、温州、フフホト、恵州、包頭、常州、西寧、連雲港、張家口などの都市も、その争奪戦に参入したのである。
省単位で見ると、人口流出の最も多い省は、河南省の1014万、安徽省の890万、四川省の777万、湖南省の650万、江西省の518万となっており、この5つの省の人口流出の割合はみな10%前後だ。
人口流出が激しい東北部よりも
環境が厳しい西安で起きた奇跡
特筆すべきことは、東北部の3つの省の人口はすでに10年連続流出しているということだ。2017年の人口データを見ると、吉林省は総人口が2717.43万人で前年同期比15.6万人の減少、黒竜江省は3788.7万人で前年同期比10.5万人の減少、遼寧省は4369.8万人で前年同期比8.9万人の減少となっている。
経済の重心が南に移るにつれ、特定の産業が突出して発達しているという産業構造が特徴的である東北地域には人が集まらず、人口流出の激化が社会現象にさえなってしまった。その影響が家庭にも大きく影を落とした。中国で離婚率が最も高いトップ5省に、東北3省が全てランク入りしており、そのうち黒竜江省の離婚率は64.13%と中国でトップになっている。興味深い現象と見る人もいるが、東北の人々の心境はまさに「泣きっ面に蜂」だろう。
中国全体から見れば、人口は西部地区、中部のいくつかの地区の人口転出規模がますます拡大しており、東部、中部のいくつかの地区の人口集中傾向はますます顕著になっている。そのなかで、一帯一路こと新シルクロード経済圏の重要な拠点となる西安市は、西部に位置しているにもかかわらず人口が増え続け、今年4月末、ついに1000万人を突破した。その実績は、訪日した副市長の発言を強気なものにした一因にもなっただろう。
(作家・ジャーナリスト 莫 邦富)
https://diamond.jp/articles/-/208994
高齢化が進む中国・西安で「高学歴の若者」が激増している奇跡高齢化が進む中国において、人口流出が激しい東北部よりも環境が厳しい西北部に位置する西安で、ある奇跡が起きている(写真はイメージです) Photo:PIXTA
西安副市長が来日時に語った
高学歴の若者が急増する背景
しばらく前、古代シルクロードの起点で、中国歴代13王朝の都として栄えた西安市から、王勇副市長一行が日本を訪れた。私は銀行出身の王副市長一行を、日本の証券会社をはじめとする金融機関や企業に案内した。
日本企業の関係者との交流の中で、企業誘致の任務を背負っている中国側の自己紹介には、耳にタコができてしまうほど常套句的な内容が多い。たとえばいつも、交通の便利さ、労働力の豊富さ、賃金の安さ、市場の大きさなどが強調される。
しかし、今回の王副市長の発言には面白い内容があり、それが私の関心を惹いた。彼が西安市の人口規模に触れたとき、2018年の1年間で、西安市には新住民といわれる市民が80万人も増えたという。また市民の平均年齢は37.39歳で、前年度よりは1歳も下がった。こうした話を、彼は誇らしげに紹介した。
つまり、新市民の中に若い人が多いから、市全体の人口の平均年齢を押し下げてくれたのだ。急速に高齢化社会となりつつある中国では、住民の平均年齢の若さがセールスポイントとなる。
もう1つ、王副市長は新市民の中身も強調した。新市民の構造を見ると、若いだけではなく、学歴も高い。その40%は大卒である。同市の大学卒業者の62.9%が西安に残りたいと言っているという調査データも、誇らしげに見せた。
その発言を聞きながら、私は中国に存在する「東北現象」と呼ばれる現象を思い起こした。ここでいう「東北」とは、旧満州だった黒竜江省、吉林省、遼寧省のことをいう。その東北現象は、つまり地域経済のマイナス成長、地元人口の他の地域への流失を表現する新語だ。
東北よりもっと環境が厳しい西北にある西安は、なぜ東北現象が起こらずに済んだのかと疑問に思う人もいるだろう。西安には大学が84校ある。大学在学生は130万人以上もいる。その大卒の若者の大半が西安に残ることを希望しているという現実が、西安の「若さ」を維持してくれた。だから、「大学が多いことが西安を窮地から救った」という説明を聞いたこともある。
高齢化社会を迎えた中国では、住民の平均年齢が若いことが都市の競争力になっているのだ。王副市長の発言を聞きながら、そのことを再度、認識させられた。
さらに深く考えると、すぐに次の現象に気づいた。中国の各地方、各都市間の競争のポイントは、これまでのGDPや企業誘致実績から、人口の増減という新しい分野へとシフトしている。しかも、その現象がすでに広く見られている。
人的移動のハードルを
壊した戸籍政策の大変動
その背後には、中国の戸籍政策の大きな変動という流れがある。今年3月に発表された『2019年新型都市化建設重点任務』という文書からも、その政策変化の一端を覗くことができる。わかりやすくいえば、中国は全面的に大型都市の戸籍登録条件を緩和し、正式に全国都市化を開始する、という号令が出されたのだ。
中華人民共和国が成立してから、中国はずっと厳しい戸籍制度を実施してきた。農村に居住している人間は農村戸籍しかもらえず、都市部への移住が厳しく制限されてきた。都市戸籍を持つ都市部の住民にとっても、規模の大きい都市への移住が非常に困難だった。
1978年から改革・開放時代が始まって、40年以上が経った。その40年間はある意味で、これまでの戸籍制度との闘いの40年間ともいえる。経済の活性化は人的流動の活発化を促進し、さらにその人的流動の活発化は、頑なに一元的な管理の下にに置かれている戸籍制度の障壁を打ち破る作業へとつながっていく。つまり改革・開放時代の40年間は、戸籍制度の解体作業の40年間ともいえる。
それでも、これまでの市街地の人口500万以上の都市では、戸籍は厳格に制限されていた。しかし今、その風向きは突然変わってきた。常住人口が100万~300万人の大都市では、全面的に戸籍制限がなくなり、人的移動のハードルはゼロとなった。常住人口が300万~500万人の大都市では、全面的に戸籍制限が緩和される。北京、上海、広東、深センなどの超大型都市では、「積分落戸制度」(ポイント政策)を整え、大幅に新市民の受け入れ枠、つまり戸籍枠を増加した。これらの大都市で真面目に仕事をしている人間なら、ほぼ間違いなくその都市の戸籍を確保できるようになったのだ。
北京、上海、深センなどに加えて、広州、天津、成都、武漢、南京、鄭州、杭州などの都市部の戸籍制限も、すべて大幅に緩和された。
日本社会を苦しめている少子高齢化の現象は、中国でも見え始めた。それはさらに「住民争奪戦」を熾烈なものにした。その意味では、住民争奪戦は数年前にすでに始まっていたのだ。国としての政策変更は、その現実を追認しただけのようなものだ。
瀋陽、ハルピン、青島、西安、合肥、昆明、太原、長春、大連、長沙、済南、アモイ、南寧、ウルムチ、蘇州、寧波、石家庄、南昌、貴陽、汕頭、蘭州、無錫、福州、洛陽、仏山、温州、フフホト、恵州、包頭、常州、西寧、連雲港、張家口などの都市も、その争奪戦に参入したのである。
省単位で見ると、人口流出の最も多い省は、河南省の1014万、安徽省の890万、四川省の777万、湖南省の650万、江西省の518万となっており、この5つの省の人口流出の割合はみな10%前後だ。
人口流出が激しい東北部よりも
環境が厳しい西安で起きた奇跡
特筆すべきことは、東北部の3つの省の人口はすでに10年連続流出しているということだ。2017年の人口データを見ると、吉林省は総人口が2717.43万人で前年同期比15.6万人の減少、黒竜江省は3788.7万人で前年同期比10.5万人の減少、遼寧省は4369.8万人で前年同期比8.9万人の減少となっている。
経済の重心が南に移るにつれ、特定の産業が突出して発達しているという産業構造が特徴的である東北地域には人が集まらず、人口流出の激化が社会現象にさえなってしまった。その影響が家庭にも大きく影を落とした。中国で離婚率が最も高いトップ5省に、東北3省が全てランク入りしており、そのうち黒竜江省の離婚率は64.13%と中国でトップになっている。興味深い現象と見る人もいるが、東北の人々の心境はまさに「泣きっ面に蜂」だろう。
中国全体から見れば、人口は西部地区、中部のいくつかの地区の人口転出規模がますます拡大しており、東部、中部のいくつかの地区の人口集中傾向はますます顕著になっている。そのなかで、一帯一路こと新シルクロード経済圏の重要な拠点となる西安市は、西部に位置しているにもかかわらず人口が増え続け、今年4月末、ついに1000万人を突破した。その実績は、訪日した副市長の発言を強気なものにした一因にもなっただろう。
(作家・ジャーナリスト 莫 邦富)
https://diamond.jp/articles/-/208994

2019-07-19
客观日本1月号(二)华裔科学家陈志坚等三人荣获日本国际奖
2026-02-03
第四届肿瘤统合治疗学术研讨会在东京大学圆满落幕
2026-01-06
滞在相談顧問:帰化した中国人の訪中
2026-01-03
中国驻日本大使吴江浩通过《人民中国》发表新年贺词
2026-01-02
《中文导报》2026新年献词:穿越寒潮 护送温暖 照亮新年
2026-01-03
新年賀正
2026-01-02
国家主席习近平发表二〇二六年新年贺词
2026-01-01
滞在相談顧問:中国人同士の日本国内での婚姻手続と婚姻の証明について
2025-12-31
北海道中国工商会・北海道中国会共催「新春交歓会」のご案内
2025-12-30
客观日本12月号(四)可选择性攻击大肠癌的海洋细菌,治疗效果显著
2025-12-26
中文导报:北海道中国会举办年会暨恳亲会
2025-12-24
客观日本12月号(二)日本科技补充预算案全貌公开
2025-12-12
东瀛万事通・今日头条・中文導報・日本东方新报:北海道中国会举办第十二届总会&恳亲忘年会
2025-12-11
第12回 北海道中国会 総会&懇親会
2025-12-07